【飯盒炊飯】方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについて

飯盒炊飯の方法概要
飯盒の使い方として中蓋や外蓋も食器代わりとなるため、野外でも重宝します。中蓋の本来の使い方とされているのがお米を計る計量カップの役割を担っていて、中蓋いっぱいにお米を入れると2合分が簡単に計れることは意外と知られていない事柄です。また軽く圧力をかけるための重量を持った蓋であることにより、吹きこぼれを防ぐことにも繋げることもできるため、飯盒選びの知恵とも言われています。その他にも、焦げ付きを抑えて後始末をラクにしたい場合にはフッ素加工が施されている製品を選ぶことや、熱伝導に優れた肉厚素材を選ぶ一工夫もポイントと言えます。
飯盒炊飯の方法その1
飯盒炊飯の調理においては、やり方や流れ1つでお米に芯や焦げのない、ふっくら美味しいご飯を炊きあげることが可能であり、飯盒炊飯の1つ目の流れとしてはお米を研ぐことが挙げられます。また、キャンプ場などの自然の中で炊飯調理する場合には、研ぐ必要がなく、環境に優しい無洗米を使う方法が最適です。3回から5回程度の研ぎ洗いを行いますが、手順として水を切る際によく行ってしまう失敗が米粒が流れてしまうことで、失敗しないやり方として研ぎ水を切る際に中蓋を少しずらしてかぶせると米粒が流れ出てしまうことを防ぐことができます。
飯盒炊飯の方法その2
家庭の炊飯器で炊く時と同様、飯盒炊飯でもお米と水の量は正確に計る必要があり、水はお米と同量です。特に水加減は炊きあがりがベチャついたり、芯が残るなどの失敗に繋がりやすいため、計量は大切です。飯盒の中蓋を使用するやり方であれば正確に水加減を計ることが可能となっており、中蓋1杯の水が2合用となります。製品によって多少の違いがあり、飯盒の内側にラインがある場合には下のラインが2合用となり、また飯盒の上蓋1杯の水は3合用である場合が一般的です。2合や4合は計りやすいものの、3合は上蓋または内側のラインの上下の間を見極めて水を加える必要があります。
飯盒炊飯の方法その3
お米を計り、研いで注ぎ、水を加える流れのまま火に掛ける方もいらっしゃいますが、美味しいご飯に仕上げるには最低30分は水に浸しておく必要があります。お米は乾燥している状態であるため、直ぐに火に掛けてしまうと芯の部分に水分が含まれていないのでカチカチのご飯に炊きあがってしまいます。水分をしっかりお米に吸収させる時間を作ることで、ふっくらとした炊きあがりに仕上げることができます。しかしながら、時間がない場合には水の量を若干多めに入れて火に掛けることで芯の残らない理想の炊きあがりに結びつけることもできます。
飯盒炊飯の方法その4
飯盒を用いり、キャンプ場などのように焚き火を使い炊飯調理する方法において、縦長の形状となる飯盒の場合には火にあたる底の面積が狭いため、水が沸騰するまでに時間も燃料も掛かってしまい効率的ではないデメリットも挙げられます。効率的な方法としては水だけをコッヘルなどの鍋に移して沸騰させ、沸騰したお湯を飯盒に移してから火に掛けます。お湯から仕上げる方法では弱火に掛けることも焦がさないポイントで、狭い底でも十分に弱火の火を受け止められます。また、上蓋に重石を乗せることもポイントで吹きこぼれを防止することができます。
飯盒炊飯の方法その5
炊きあがりは音と香りで判断します。飯盒炊飯でのおおよその時間は水が沸騰してから約15分と言われていて、手順としては弱火で10分ほど火に掛け、沸騰のサインとなる湯気が出てきたら強火にし、吹きこぼれを防止する重石を乗せ、強火で15分ほど火に掛けます。徐々に蒸気の量も減り出し、チリチリという焼けるような音と共に鼻を近づけると甘い香りと香ばしい匂いが漂うので、その音と香りが炊きあがりの目安となります。一般的に赤子泣いても蓋取るなと言われていますが、芯が残っていることもあるため、1度蓋を開けて中を確認することも初めての場合にはポイントとなります。
飯盒炊飯の考察
この時、ご飯に固さが残っている場合の対策として水を少し飯盒の中に入れて、数分火に掛けることで固さのない仕上がりが期待できます。また、美味しいご飯を食べるにはこの後、5分から10分程度の蒸らしの時間を取る必要があります。飯盒を逆さにする使い方も提案されていますが、その理由としては熱がもっとも底に集中しているため、そのまま蒸らしてしまうと底のご飯がおこげではなく真っ黒に焦げついてしまうためであり、蒸らす時に飯盒を逆さにするのが一般的です。蒸らしの時間を経て、しゃもじを使い底から持ち上げるようにかき混ぜます。
飯盒炊飯のまとめ1
キャンプなどの焚き火を使って炊飯調理を行う場合には、ススで外側が真っ黒に焦げてしまいますし、内側は米粒がくっついてしまい固まっている状態に陥りやすく、調理前後のお手入れ方法も知っておきたい事柄です。フッ素加工が施されていないアルミ製品はゴシゴシ洗いで変形してしまいやすく、ご飯を炊く前には外側の部分にクレンザーを水で溶いてペースト状にしたものを塗り広げて保護することがポイントとなります。クレンザーがスス汚れなどを吸収して固まってくれるため、黒くなる心配もなく、万が一中身が吹きこぼれても調理後の後片付けをラクにしてくれます。
飯盒炊飯のまとめ2
また、クレンザーである分、洗う際にも研磨効果がありラクに汚れを落とし洗いできます。飯盒炊飯ではご飯が温かいうちに食器によそい、できるだけ早く水またはお湯に浸けておく一手間も大切です。冷めてしまうことで米粒が固まってしまい、内側にペタッとくっついて洗いにくくなりやすいためで、手入れ方法までも視野に入れて炊飯調理を楽しむことも大切です。自然の中でのキャンプなどの場合は環境にも配慮する必要もあって、洗剤などを用いることなくすんなり洗い物が済む一工夫は食べるだけや調理するだけではない、大切な事柄と言えます。
飯盒炊飯の方法の注意点
また、飯盒炊飯調理では、ご飯が冷めてしまった場合には雑炊などの汁物を入れて火にかけることで冷めたご飯も美味しく食べることができますし、後片付けも汁気を加えたことによってラクに行えます。また、飯盒の内側は多少ならば強く擦っても平気で、焦げ付きを残してしまうと次回炊く際にそこから焦げ付いてしまったり、全体に芯があり、下は真っ黒で上はベチャついたご飯が炊きあがってしまう場合があるため、内側はしっかり洗います。逆に外側は変形しない程度に留めたスス洗い程度に留め、しっかり乾燥させて保管することもポイントとなります。
-

-
ゆうちょ振替の方法・やり方・手順や使い方
通常の銀行の振込みは相手先が自分の銀行と同じ銀行の口座をもっていて振り込む場合でも手数料がかかります。でも、ゆうちょの場...
-

-
生しいたけ保存の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて
冷蔵庫で生しいたけ保存する場合、冷蔵庫の温度は5度が最適だと言われています。保存のやり方は、冷えすぎないようにひとつずつ...
-

-
あさり砂抜きの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて
あさり砂抜きをするなら大きい網カゴで余裕を持ってやると失敗しづらいです。網付きのバットや食器洗いカゴなどを使います。バッ...
-
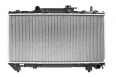
-
ラジエターの交換方法・やり方・手順や使い方
今の自動車に使われているラジエターは、かなり丈夫になっていますからそう簡単には壊れません。ですが消耗品であることには変わ...
-

-
にんにく収穫の方法・やり方・手順や使い方
にんにく収穫の時期は越冬後の2月上旬から3月下旬に行います。収穫の目安はおよそ8か月越冬させ、葉先が枯れた、葉の2から3...
-

-
誤嚥対処の方法・やり方・手順や使い方
誤嚥の対策には食事にとろみをつけてのどからスムーズに胃の中に滑り込ませる方法が有効な方法です。自分の力で呑み込めないなど...
-

-
襖の張り替え方法・やり方・手順や使い方
襖張り替えはDIYの第一歩だと言えます。二人以上の人員と少しの道具で気軽に部屋の模様替えができます。ホームセンターで襖紙...
-

-
いちごの肥料の方法・やり方・手順や使い方
いちご肥料は行う時期により種類が異なってきます。まず肥料としては二月の下旬ごろに行います。この際に行う肥料の種類としては...
-

-
PDFの方法・やり方・手順や使い方
PDFというファイル形式をご存知でしょうか。Portable Documents Formatの頭文字をとった物です。パ...
-

-
【咳を止める飲み物】方法・手順・使い方、メリットデメリットな...
風邪の代表的な症状として咳が止まらないというものがあり、のどや気管に炎症が起こっている時に発生すると言われています。一般...





キャンプで用いることの多い調理道具の1つが飯盒で、ご飯を炊くために利用することができ、飯盒を利用するにあたり、使い方や手順などの知識もある程度必要となります。一般的に飯盒として提供されている形には兵式と丸形があり、飯盒はご飯を炊く専門の調理道具としてだけではなく、現在では鍋として様々な調理に使える道具とされています。また、使い方でもっとも難しいとされる火加減についても、手順通りにこなしていてもタイミングは図りにくく、蓋のカタカタ音で知らせてくれる飯盒も提供されていて、誰でも失敗することなくご飯を炊きあげることが可能になっています。