ラインをパソコンで使う方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについて
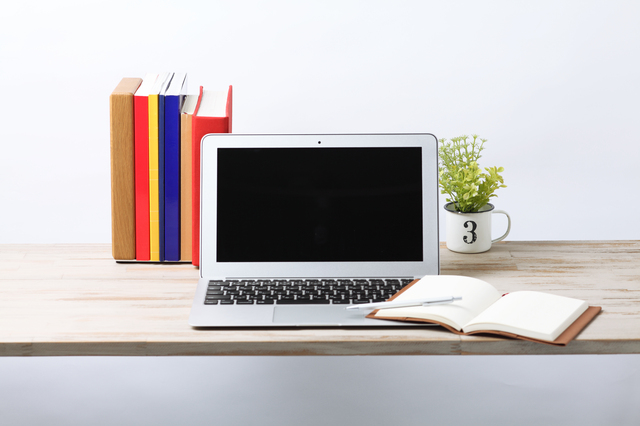
ラインをパソコンで使う方法概要
ラインをパソコンで使う為には電話番号の認証かfacebookの認証が必須となります。現在、ラインを利用している方で同じアカウントを利用するのであれば、以前登録した携帯電話等の認証で問題ありません。 新しくアカウントを作る場合は新規登録の手順に従って登録しなければなりません。 新規登録の手順はLINEを起動すると自動的にアナウンスされて出てきますのでアナウンスの登録手順の流れに従って登録を完了してください。 FACEBOOKのアカウントで新規登録する方法は利用者登録の画面でFACEBOOKでログインという項目が一番下にでてきますので、そちらをクリックします。
ラインをパソコンで使う手順・方法01
新規登録が完了しましたらLINEの利用規約が出てきます。利用規約を確認したら同意をクリックします。 同意をクリックするとプロフィール設定方法の画面に切り替わります。 ここではLINEに表示される名前(ニックネーム)と画像(プロフィール写真)を設定する事ができます。FACEBOOKで認証した場合はFACEBOOKでの名前と写真が自動的に設定されます。 名前や画像をfacebookと同じものを使いたくない方はここで設定し直す必要があります。 やり方は変更したい項目をクリックして、変更・画像選択することで簡単に行えます。 これで初期登録の一連の流れは終了です。
ラインをパソコンで使う手順・方法02
初期登録が終わったらパソコンからLINEにログインします。 ログインすると処理が行われます。 本人確認のアナウンスが出て、認証パスワードが送られてくるので送られてきた認証パスワードを入力します。 PC版LINEではスマートフォン等と同一アカウントで連動してログインする際は、設定画面で”他端末からのログイン許可”の項目にチェックが入っていないとPCからログインすることが出来ません。 設定方法はホーム画面から設定→アカウント→ログイン許可のチェックボックスをチェックです。 これでPCからのログインも可能になります。
ラインをパソコンで使う手順・方法03
新規登録された方は基本情報の設定を行います。スマートフォン等と連動している方は同じ設定内容で同期されてます。 まずはホーム画面から設定をクリックして基本設定を行います。 基本設定のログイン画面ではパソコンを起動したら同時に起動する設定も可能です。 名前、ひとこと、ID、ID検索、言語設定が可能です。 IDの検索を許可の項目にチェックが入っていないと検索されても非表示になってしまいます。 よくID検索しても出てこないという事を聞きますが、これが原因です。IDで登録を希望される方は必ずチェックを入れてください。
ラインをパソコンで使う手順・方法04
LINEの通知設定では通知サウンド、サウンド(通知音)、バイブレーション、LED、通知表示、ポップアップの表示・非表示が設定できます。 他にも一時停止という機能もあり、午前8時まで停止と1時間停止することが可能です。 これらを設定する事で寝ている時間帯や大事な会議などの時間に通知音がなってしまうという事態を回避する事が可能です。自分の生活スタイルにあった使い方が出来るように設定する事でLINEの利便性はあがります。 通知設定でポップ表示をONにすると、表示されたPOPを確認することで既読が付かずにメッセージを確認する事が可能です。
ラインをパソコンで使う手順・方法05
LINEは多くの人と繋がるとゲームの招待などが頻繁に送られてきて困る場合もあります。 しかし、個別設定をすることにより、こういった招待メッセージを排除する事も可能です。 設定方法は個別設定→連動アプリ・連動していないアプリから行えます。 この設定を行っていないと、全く興味のないゲームの招待や通知などが頻繁に送られてきてしまう可能性があります。こういったメッセージは友人登録してある人へ無差別に送られ、決して送ってくる人に悪意があるわけではありません。しかし、興味の無いメッセージを頻繁に送られてくる方としては良い印象はありません。お互いの関係を壊さない為にもしっかりと設定しておくべきでしょう。
ラインをパソコンで使う考察
トーク・通話設定では文字のフォントやサイズの変更が可能です。自分の好みの設定すると良いでしょう。 また通話の着信許可設定ではチェックボックスにチェックが入っていないと、一切、着信されませんので注意が必要です。 友達管理ではブロックリストや表示リストを確認できます。ここではブロックの解除や削除も可能です。 ブロックリストから削除すると再びIDやQRコードからの友達登録をやり直さないとこちらには表示されませんが、相手側からのメッセージは送られてきております。メッセージはこちらには表示されておりませんので既読になることはありません。
ラインをパソコンで使う方法まとめ01(使い方や注意点など)
タイムラインの公開・非公開設定では個別に設定する事が可能です。 やり方は簡単でひとり、ひとりに公開と非公開のチェックボックスがあるので、そこにチェックを入れるだけです。 友達には見て欲しいけど、会社の人には見られたくないという人などには嬉しい機能です。一部の人に公開設定をすることで一部の人に気を使うことなくタイムラインの投稿を活用できます。 また新しい友達に自動公開というチェックボックスもあります。ここにチェックを入れると新しく友達になった人には自動的にタイムラインを公開する事になりますので、注意が必要です。
ラインをパソコンで使う方法まとめ02(使い方や注意点など)
パソコン版LINEでは画像・音声・動画データの他にもファイルの添付が可能です。添付可能なデータはword、excel、PDF、power pointの4種類です。こういったファイルの添付が可能なのでパソコンからLINEを使用する方も増えております。使い方は人それぞれですが、ビジネスシーン等でも非常に活用されております。 ただファイルのデータ量の制限もあるので、送信できたかどうかを確認する事を推奨します。特に動画などの大きいファイルはデータ量ではじかれる事も多いです。データ量が多く送信不可の場合は送信時にメッセージが表示されます。
ラインをパソコンで使う方法まとめ03(使い方や注意点など)
パソコンでラインを利用する事は決して難しいことではありません。設定の流れなどもアナウンスにしたがって進めるだけので簡単ですし、スマートフォンと連動の場合は特に設定はいりません。個人的に同一アカウントでパソコンとスマートフォンで連動させるというやり方は大変おすすめです。ただ不特定多数の方が使用するPCから利用する場合は必ずログアウトして終わらせるようにしないとなりません。知らない方にあなたの個人情報が漏洩する事になり兼ねません。注意しましょう。 LINEで大人気のスタンプですが、以前に購入したスタンプはPCでも利用が可能です。
-

-
ガス抜きの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて
ガスが溜まってしまうと、苦しくて辛いですね。ガスが溜まるのには、きちんと理由があります。まず、長時間座っていたり、ストッ...
-

-
【神社参拝】方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについ...
日本には、人生の節目に神社参拝をして祈願する風習があります。たとえば、生まれてから約1ヶ月目に、地域の神社に挨拶し、健や...
-

-
柿木接ぎ木の方法・やり方・手順や使い方・流れ
接ぎ木を行うことで、複数の樹木の性質を持たせたり、樹木の成長を補うことができます。接ぎ木は新芽が芽吹く季節に行うのが良く...
-

-
朝日新聞解約の方法・やり方・手順や使い方
朝日新聞を解約する際に注意しなければならないのは、引き止めに対する態度です。 申し込み自体は専用の番号に電話すれば良い...
-

-
お腹のガス抜きの方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて
お腹には食べ物が消化された後や、便などが蓄積した時などにガスが溜まってしまうことがあります。そのガスは、多量に溜まると腹...
-

-
茄子の保存方法・やり方・手順や使い方
茄子の旬は6月~9月で夏野菜になります。保存温度は10℃~12℃で寒いところが苦手です。5℃以下になると身が縮んで低温障...
-

-
ITUNESの使用方法・やり方・手順や使い方・流れなどについ...
ITUNESとは、音楽や映画などを購入できたり、iPhoneやiPodなどの端末に音楽を入れたりすることができるパソコン...
-

-
筋トレの方法・手順・使い方、メリットデメリットなどについて
人間の資本は何と言っても体であることは言うまでもありません。体が健康でないと、何もする事が出来ないからです。また、精神面...
-

-
スイッチ配線の方法・やり方・手順や使い方
電気機器のスイッチが故障して動作しなくなってしまった場合、配線を行う必要があります。多くの電気機器の電源ボタンはほぼ同じ...
-

-
ブロック積み施工の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについ...
皆さんの中で、お庭や敷地の境界にブロック積み施工を、自分自身で行いたいという方もいらっしゃると思います。 そこで今...






ラインはPCからでも利用でき、使い方も簡単です。
ラインをパソコンで利用する為にはまず、アプリ(ソフト)のインストールが必要となります。まずPC版LINEをダウンロードできるページへ移動します。ページの探し方ですがgoogleやyahooなどの検索エンジンから”LINE、ダウンロード”と検索すればすぐに出てきます。MACの方はMAC APP STOREからダウンロードしてください。ダウンロードが終わりましたら、起動できるようにパソコン内にインストールします。インストールが終わりましたら、起動出来ているかを確認してください。対応していないパソコンの場合は起動しても正確に動作しない場合もあります。