囲碁の方法・やり方・手順や使い方
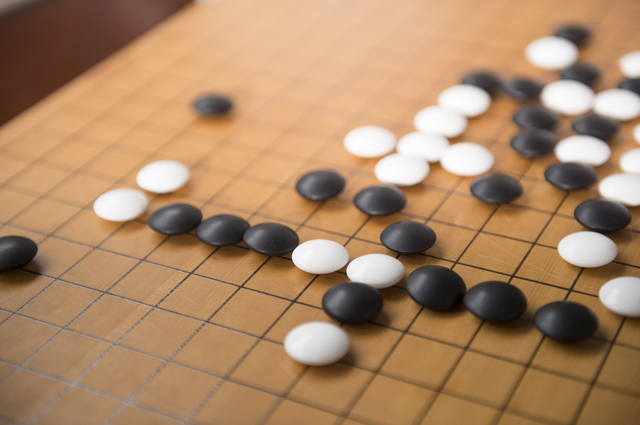
囲碁の方法概要
囲碁を誰かとする時はまず最初に、ゲームをするための道具を用意しなければいけません。このゲームは碁盤と碁石が必要なので、その2つを買ってくる必要があります。碁石などではなくパソコンを利用してやる場合は、専用のソフトウェアを購入します。そうやって道具を購入した後は実際に遊ぶことになりますけど、あらかじめ基本的な知識は持っておいたほうがいいです。このゲームはルールはシンプルなのですが、他のものに比べると複雑なところが多いです。ですのでこのゲームをする時は最初に、碁石などの使い方についてよく学ぶ必要が大事です。
囲碁の手順・方法01
碁石や碁盤を使ってゲームをする時は、その手順について知っておくことが重要です。そのやり方とはまず最初にハンデをつけるために、弱い方の人があらかじめいくつかの碁石を碁盤に置いておきます。そうするとその碁石の分だけ有利になるので、力量に応じて差をつけておくといいです。実際のゲームでは互いに碁石を一つづつ起き、相手の碁石を囲むことができれば取ることが可能です。そうやってゲームを続けていき、碁盤が埋まってきたらゲームは終了します。ゲームが終了した時は相手からとった碁石と、自分が保持している碁石で囲った範囲がポイントになります。
囲碁の手順・方法02
囲碁で使う用具は、碁盤と碁石および碁石を入れておく碁笥の3つです。碁盤は、ほぼ正方形の板に縦横19本の黒線が引いてあるものを使います。この19本黒線は4隅が2本の線、辺が3本、その他は4本の線が交差している点があり、その数は361点あります。碁石は、白と黒の丸い石を使います。高級品は、白がはまぐり、黒が那智石でできていますが、プラスチックでできているものが安価で手に入れやすいです。碁笥は、碁石を入れておくためのもので、上蓋がついています。上蓋の使い方は、蓋の役目ばかりでなく、ゲーム中に取った相手の石を入れておく役目もあります。
囲碁の手順・方法03
ゲームは対局とも呼ばれますが、進め方の手順は、黒石を持った方と白石を持った方が交互に盤上の黒線の交点に石を置いていきます。ハンデのない互先では、黒から先に石を置きます。最初から盤上に黒石をいくつか置いてあるハンデ戦では、白から石を置きます。ある交点に置かれた石が、周りを全て相手の石で囲まれますと盤上から取り上げられて相手の碁笥の蓋に入れられます。これは、一連の石の集団に対しても適用されます。最終的に勝負を決するのは、石で囲まれた陣地(地)の多さです。陣地は碁盤の黒線の交点1点を1目といって、白黒何目あるか数えて目数の多いほうが勝ちです。ただ、互先ではコミというハンデが白に与えられています。
囲碁の手順・方法04
囲碁といいますと19路盤を使って行うものを指します。こちらはこちらで古くから有りますので、定石や死活、寄せに関する書籍などが手に入れやすく、インターネット上にも情報があふれていて、学ぶには事欠きません。一方で、近年になって、主に初心者用にはじめられた9路盤を使うものが、専門棋士にも広まっています。こちらは、19路盤とは少し趣がことなり、勝負が早く、それでいて勝負が簡単につかない面もありますので十分楽しめます。また、19路盤より圧倒的に目数の少ない9路盤ですが、互先では、黒にかされるコミというハンデが、19路盤と同じことが多いのも9路盤の面白いところです。
囲碁の手順・方法05
このゲームは、普通は相手がいないと出来ませんが、一人でもパソコンソフトなどを使うとできます。ところで、今、面白いのは、ネットの9盤のオンラインゲームです。19路盤のゲームソフトやコンピューター相手のオンラインゲームは、その棋力が将棋ほどでないため少し強い人には物足りないものです。しかし、9路盤ですと、棋力もある程度ありますので、コンピューター相手でもいい勝負ができます。このようなオンラインゲームの使い方は、検索エンジンなどでゲームサイトを探して、そのサイトに書いてある手順で対局ページにたどり着きます。実際に対局してみますと結構強いので、ウデに自身のある人は試してみたらいかがでしょう。
囲碁の考察
囲碁とは、二人で行うボードゲームです。交互に盤上に石を置いていき、自分の石で囲んだ領域の広さを競います。主なルールは5つです。1つ目は、基盤の線の交差部分に黒と白が交互に打たなければならないということです。2つ目は、地(自分の領域)の多い方が勝利ということです。3つ目は、相手の石は上下左右を囲うととれて自分の領域になります。4つ目は、着手禁止点(自殺手)となってしまいます。5つ目は、コウといって、お互いが交互に合相手の石を取り、無限に続きうる形になってしまうことを言います。ゲームの目的は、自分の色の石によって盤面のより広い領域を確保することです。
囲碁のまとめ01(使い方や注意点など)
現代日本の囲碁プロ組織として「日本棋院」と「関西棋院」があります。この2つの組織によりプロを認定する入試試験を行っています。プロ入りには年齢制限があり23歳以下のみに開かれた狭き門として多くの若者がプロを目指すべく、日々精進しています。また、このプロ組織は日本のみならず中国や韓国、朝鮮にもあるため、世界大会として試合が行われています。その上、昨今ではアメリカや欧州でも協会が設立され、プロとして活躍する棋士が増えてきています。その広がりはオーストラリアやアルゼンチンなど世界各国に広がりつつあります。
囲碁のまとめ02(使い方や注意点など)
日本における囲碁の起源は奈良時代の遣唐使となります。この遣唐使により中国大陸から日本に伝わったとされています。その他の起源の説としては当時の朝鮮半島百済より伝来したとも言われています。日本最古の碁盤とされているものは奈良県の東大寺正倉院の碁盤です。また、日本において全国的に広まったのは室町時代とされています。公家中心の文化から武家中心の文化への変化が日本各地に広まったきっかけとなりました。その後、大正13年に日本棋院が設立され、日本において更なる発展と広がりを遂げるようになりました。今では関西棋院とともに日本のみならず世界で活躍するプロを輩出する組織となっています。
囲碁のまとめ03(使い方や注意点など)
日本には、昔から囲碁というものがあります。今回は、そのやり方や方法について考えてみることにしましょう。まずは、どういったルールなのかということです。基本的なものは、より多くの陣地をとるといういわゆる陣取りゲームであります。黒と白の石があり、先番は黒になるのですが決め方には、にぎりというもので決めます。どちらか一方が、石をいくつか握りその数が奇数か偶数かをもう一方が石を奇数個または偶数個置き、そのあたりはずれで決まります。そしてはじまり、相手の石を囲むことでその意思を無力化できるのです。生きるためには、二眼必要になりそのためのやり取りが魅力と言っていいでしょう。
-

-
梅接木の方法・やり方・手順や使い方
接木とは、2つ以上の種類の植物を接ぎあわせて、両方の特徴を兼ね備えた1つの植物を作り出すことです。上部に接ぎあわせる植物...
-

-
ふるさと納税計算の方法・手順・使い方、メリットデメリットなど...
ここ1年間で耳にすることの多くなったふるさと納税。耳にはしていても、実際にどういう制度なのか、どういうやり方で行えばいい...
-

-
巨峰の剪定の方法・やり方・手順や使い方
巨峰剪定は、樹木の活動が止まる1~3月の寒い時期に行います。まず最初に、枝が込み入った部分の剪定を行います。この際には、...
-

-
タオル体操の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて
女性はもちろん、男性もメリハリの効いたボディ作りに運動を取り入れているケースは多いものの、無酸素運動に使われるマシンの使...
-

-
WINDOWS7修復の方法・やり方・手順や使い方
WINDOWS7の修復方法についてです。ここでは、システムの復元を実行する方法で対処します。スタート、コントロールパネル...
-

-
スマホ画面をテレビで見る方法・やり方・手順や使い方
スマホの画面をテレビで見るには、無線LANなどを利用することで可能です。 その他にも携帯自体に画面をテレビに映し出すミ...
-

-
エクセル両面印刷の方法・やり方・手順や使い方
エクセルで作成した資料を両面の印刷をする方法です。ここでは、Excel 2013の場合について記述します。まず、印刷した...
-

-
SUICAをコンビニで購入する方法・やり方・手順や使い方
最近はほとんどのコンビニエンスストアが電子マネーでの支払いに対応しています。電子マネーのメリットはタッチひとつで購入が完...
-

-
ゴーヤ水の方法・やり方・手順や使い方
乾燥肌、敏感肌に適しているゴーヤ水は、へちま水より保湿力が高く刺激が少ないローションになります。ゴーヤの収穫が終わったら...
-

-
エクセル割り算の方法・やり方・手順や使い方
エクセルでの割り算では除算演算子「/」を使用します。「/」は算数の「÷」と同様の意味の記号です。例えば、「100÷5」を...






将棋と並んで日本を代表するゲームが囲碁です。しかし色々なルールがあるため、初心者には取っつきにくい面があります。かつては碁会所などへ通いながら手ほどきを受けるのが最も早道でしたが、最近ではパソコンやスマホなどのゲームを利用するケースが増えています。このようなゲームを利用するメリットは、初心者にもわかりやすくなっているからです。昔なら碁の本などを読みながら勉強したのですが、ゲームですと遊びながらルールを学ぶことができます。またネットを介した対戦もできるので、競争心がわいて上達も早くなります。実戦の中で覚えられるのがゲームの良いところです。